| 閉じる |
| 【考案の名称】携帯情報端末テーブル 【国際特許分類】 H04M 1/11 (2006.01) 【FI】 H04M 1/11 Z 【実用新案権者】 【識別番号】525212238 【氏名又は名称】須藤 貴光 【住所又は居所】茨城県古河市下山町1-38 リバータウンA202 【代理人】 【識別番号】100089026 【弁理士】 【氏名又は名称】木村 高明 【考案者】 【氏名】須藤 貴光 【住所又は居所】茨城県古河市下山町1-38 リバータウンA202 【要約】 【課題】携帯情報端末の操作が行いやすい携帯情報端末テーブルを提供する。 【解決手段】携帯情報端末を上に載せることができる折畳み可能なテーブルと、使用者の肩にかけて前記テーブルを使用者の身体前面に支持できるストラップと、を備える携帯情報端末テーブルであって、前記テーブルは、端部において相互に回動可能に軸着された複数の棒状フレームと、前記棒状フレームが展開した場合に棒状フレーム間で展張される布材又はビニール布材による幕部と、を有し、前記複数の棒状フレームの展開時には方形状の前記テーブルを形成すると共に、前記複数の棒状フレームの折り畳み時には棒状体を形成し、前記ストラップは、前記テーブルの対角線の両端の部位に取り付けられ、展開時には、前記ストラップを使用者の肩にかけて前記棒状フレームを展開させて前記テーブルを形成し、前記テーブルの上に前記携帯情報端末を載せて前記携帯情報端末を操作可能とする。 【選択図】図1 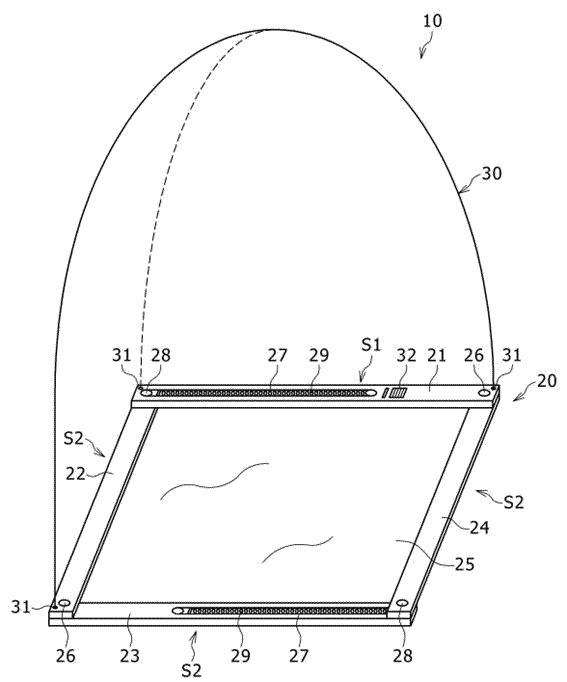 【実用新案登録請求の範囲】 【請求項1】 携帯情報端末を上に載せることができる折畳み可能なテーブルと、 使用者の肩にかけて前記テーブルを使用者の身体前面に支持できるストラップと、を備える携帯情報端末テーブルであって、 前記テーブルは、端部において相互に回動可能に軸着された複数の棒状フレームと、前記棒状フレームが展開した場合に棒状フレーム間で展張される布材又はビニール布材による幕部と、を有し、 前記複数の棒状フレームの展開時には方形状の前記テーブルを形成すると共に、前記複数の棒状フレームの折り畳み時には棒状体を形成し、前記ストラップは、前記テーブルの対角線の両端の部位に取り付けられ、 展開時には、前記ストラップを使用者の肩にかけて前記棒状フレームを展開させて前記テーブルを形成し、前記テーブルの上に前記携帯情報端末を載せて前記携帯情報端末を操作可能とすることを特徴とする携帯情報端末テーブル。 【請求項2】 対向する一対の前記棒状フレームを二組備え、 前記二組の棒状フレームは、端部同士が軸部により回動可能に接続されており、 対向する一の一対の前記棒状フレームには、それぞれ溝部が長さ方向に沿って開設され、 対向する他の一対の前記棒状フレームの端部に設けられ、互いに対角線上において配置された一の一対の軸部は、前記溝部内にスライド可能に配設されて移動軸部として構成されると共に、対向する他の一対の前記棒状フレームの端部に設けられた他の一対の軸部は固定軸部として構成され、 前記棒状フレームの前記溝部内には、前記一の一対の軸部を常時、前記端部外方へ付勢するスプリングが配設されている、ことを特徴とする請求項1記載の携帯情報端末テーブル。 【請求項3】 前記対向する他の一対の軸部の間には、棒状接続フレームが、前記軸部に対して回動可能に配置されていることを特徴とする請求項2記載の携帯情報端末テーブル。 【請求項4】 前記複数の棒状フレームは、それぞれ異なる長さの部材により形成され、端部において単一の軸部により回動可能に軸着され、 前記複数の棒状フレームは、収納時には単一の棒状体を形成すると共に、展開時には、前記棒状フレームが前記方形状のテーブルの一片部及び隣接する他片部を形成し、他の棒状フレームはその間に配置されることを特徴とする請求項1記載の携帯情報端末テーブル。 【請求項5】 前記幕部は、透明、不透明、色付き、又は、ハーフミラーのいずれかであることを特徴とする請求項1記載の携帯情報端末テーブル。 【考案の詳細な説明】 【技術分野】 【0001】 本考案は、携帯情報端末テーブルに係り、特に、使用者の肩にかけて使用することができる携帯情報端末テーブルに関する。 【背景技術】 【0002】 一般に、スマートフォンを屋外で操作する場合、一方の手でスマートフォンを保持しつつ、他方の手でスマートフォンの操作、文字入力を行う必要がある。 この場合、一方の手で荷物を持っているような場合には、スマートフォンの操作を行うことは困難である。また、電車の座席に着座しているような場合には、スマートフォンの操作が非常やりにくい場合がある。 特許文献1〜5は、スマートフォン等に関する様々な技術を開示しているが、携帯情報端末の操作が行いやすい携帯情報端末テーブルは存在しない。 【先行技術文献】 【特許文献】 【0003】 【特許文献1】 特開2024−062654号公報 【特許文献2】 実用新案登録第3230868号公報 【特許文献3】 特許第6810732号公報 【特許文献4】 特開2020−057996号公報 【特許文献5】 特許第6577212号公報 【考案の概要】 【考案が解決しようとする課題】 【0004】 そこで、本考案の課題は、携帯情報端末の操作が行いやすい携帯情報端末テーブルを提供することにある。 【課題を解決するための手段】 【0005】 上記課題達成のため、請求項1記載の考案にあっては、携帯情報端末を上に載せることができる折畳み可能なテーブルと、使用者の肩にかけて前記テーブルを使用者の身体前面に支持できるストラップと、を備える携帯情報端末テーブルであって、前記テーブルは、端部において相互に回動可能に軸着された複数の棒状フレームと、前記棒状フレームが展開した場合に棒状フレーム間で展張される布材又はビニール布材による幕部と、を有し、前記複数の棒状フレームの展開時には方形状の前記テーブルを形成すると共に、前記複数の棒状フレームの折り畳み時には棒状体を形成し、前記ストラップは、前記テーブルの対角線の両端の部位に取り付けられ、展開時には、前記ストラップを使用者の肩にかけて前記棒状フレームを展開させて前記テーブルを形成し、前記テーブルの上に前記携帯情報端末を載せて前記携帯情報端末を操作可能とすることを特徴とする。 従って、請求項1記載の考案にあっては、折り畳み時は棒状体となるためコンパクトに持ち運ぶことができ、使用時には使用者の身体前面に方形状の大きなテーブルを展開することができる。 【0006】 請求項2記載の考案にあっては、対向する一対の前記棒状フレームを二組備え、前記二組の棒状フレームは、端部同士が軸部により回動可能に接続されており、対向する一の一対の前記棒状フレームには、それぞれ溝部が長さ方向に沿って開設され、対向する他の一対の前記棒状フレームの端部に設けられ、互いに対角線上において配置された一の一対の軸部は、前記溝部内にスライド可能に配設されて移動軸部として構成されると共に、対向する他の一対の前記棒状フレームの端部に設けられた他の一対の軸部は固定軸部として構成され、前記棒状フレームの前記溝部内には、前記一の一対の軸部を常時、前記端部外方へ付勢するスプリングが配設されている、ことを特徴とする。 従って、請求項2記載の考案にあっては、収納時には、軸部を中心に回動させて棒状フレームを重ねて一本の棒状体にし、この状態で収納して持ち歩くことができる。また、収納時は、軸部がスプリングを圧縮した状態で溝部内の端部に位置することとなる。 【0007】 請求項3記載の考案にあっては、前記対向する他の一対の軸部の間には、棒状接続フレームが、前記軸部に対して回動可能に配置されていることを特徴とする。 従って、請求項3記載の考案にあっては、棒状接続フレームが斜めに配置される。 【0008】 請求項4記載の考案にあっては、前記複数の棒状フレームは、それぞれ異なる長さの部材により形成され、端部において単一の軸部により回動可能に軸着され、前記複数の棒状フレームは、収納時には単一の棒状体を形成すると共に、展開時には、前記棒状フレームが前記方形状のテーブルの一片部及び隣接する他片部を形成し、他の棒状フレームはその間に配置されることを特徴とする。 従って、請求項4記載の考案にあっては、使用時には正確に方形状に展開可能である。 【0009】 請求項5記載の考案にあっては、前記幕部は、透明、不透明、色付き、又は、ハーフミラーのいずれかであることを特徴とする。 従って、請求項5記載の考案にあっては、幕部のバリエーションを増加させることができる。 【考案の効果】 【0010】 請求項1記載の考案にあっては、携帯情報端末を上に載せることができる折畳み可能なテーブルと、使用者の肩にかけて前記テーブルを使用者の身体前面に支持できるストラップと、を備える携帯情報端末テーブルであって、前記テーブルは、端部において相互に回動可能に軸着された複数の棒状フレームと、前記棒状フレームが展開した場合に棒状フレーム間で展張される布材又はビニール布材による幕部と、を有し、前記複数の棒状フレームの展開時には方形状の前記テーブルを形成すると共に、前記複数の棒状フレームの折り畳み時には棒状体を形成し、前記ストラップは、前記テーブルの対角線の両端の部位に取り付けられ、展開時には、前記ストラップを使用者の肩にかけて前記棒状フレームを展開させて前記テーブルを形成し、前記テーブルの上に前記携帯情報端末を載せて前記携帯情報端末を操作可能とすることから、折り畳み時は棒状体となるためコンパクトに持ち運ぶことができ、使用時には使用者の身体前面に方形状の大きなテーブルを展開することができるため、携帯情報端末(例えば、スマートフォン)を屋外で操作する場合、特に、電車やバス等の交通機関利用時に携帯情報端末を操作する場合、片手で携帯情報端末を支持する必要がなく、携帯情報端末の操作が行いやすい。また、座席に着座する際等に一方の手で携帯情報端末を支持し、他方の手で携帯情報端末の操作を行う場合には、両方の手が体の両側に張り出し、両側に座っている人の迷惑になる可能性があるが、本構成によれば、携帯情報端末を自分の身体の前に配置できるテーブルの上に載せた状態で、片手で携帯情報端末の操作ができるため、片手で携帯情報端末の支持を行う必要がないことから非常に便利であり、かつ、他人に迷惑をかける可能性も低減できる。さらに、一方の手で荷物を持っている場合にも、荷物を持ったままで携帯情報端末の操作、文字入力を行うことができる。 【0011】 請求項2記載の考案にあっては、対向する一対の前記棒状フレームを二組備え、前記二組の棒状フレームは、端部同士が軸部により回動可能に接続されており、対向する一の一対の前記棒状フレームには、それぞれ溝部が長さ方向に沿って開設され、対向する他の一対の前記棒状フレームの端部に設けられ、互いに対角線上において配置された一の一対の軸部は、前記溝部内にスライド可能に配設されて移動軸部として構成されると共に、対向する他の一対の前記棒状フレームの端部に設けられた他の一対の軸部は固定軸部として構成され、前記棒状フレームの前記溝部内には、前記一の一対の軸部を常時、前記端部外方へ付勢するスプリングが配設されていることから、収納時には、軸部を中心に回動させて棒状フレームを重ねて一本の棒状体にし、この状態で収納して持ち歩くことができ、また、収納時は、軸部がスプリングを圧縮した状態で溝部内の端部に位置することとなるため、使用時には、手で棒状フレームを開くと、圧縮したスプリングが開放され、付勢力により軸部を押圧し、軸部は溝部内を他端部方向へ移動することにより、他の一対の棒状フレームは一の棒状フレームと共に方形枠を形成し、その間に展張された幕部も展開し、携帯情報端末が置けるテーブルを形成することができる。 【0012】 請求項3記載の考案にあっては、前記対向する他の一対の軸部の間には、棒状接続フレームが、前記軸部に対して回動可能に配置されていることから、棒状接続フレームが斜めに配置されるため、斜めに配置された、棒状接続フレームにより、展開時における全体の強度が増大する。 【0013】 請求項4記載の考案にあっては、前記複数の棒状フレームは、それぞれ異なる長さの部材により形成され、端部において単一の軸部により回動可能に軸着され、前記複数の棒状フレームは、収納時には単一の棒状体を形成すると共に、展開時には、前記棒状フレームが前記方形状のテーブルの一片部及び隣接する他片部を形成し、他の棒状フレームはその間に配置されることから、使用時には正確に方形状に展開可能であるため、テーブルについては扇子の方式を利用して展開させながら、使用時には扇状ではなく携帯情報端末を置きやすい方形状に展開可能である。 【0014】 請求項5記載の考案にあっては、前記幕部は、透明、不透明、色付き、又は、ハーフミラーのいずれかであることから、幕部のバリエーションを増加させることができるため、様々な用途に適した幕部とすることができる。 【図面の簡単な説明】 【0015】 【図1】第1実施形態に係る携帯情報端末テーブル10を示す図である。 【図2】第1実施形態に係る携帯情報端末テーブル10の展開時、格納中及び格納時の状態を示す図である。 【図3】第1実施形態に係る携帯情報端末テーブル10の使用方法を示す図である。 【図4】第2実施形態に係る携帯情報端末テーブル10−2を示す図である。 【図5】第3実施形態に係る携帯情報端末テーブル10−3を示す図である。 【考案を実施するための形態】 【0016】 以下、本考案に係る一実施の形態(第1実施形態、第2実施形態、第3実施形態)について、図面を参照しながら説明する。なお、各図面においては、理解を容易にするために、部材の形状や寸法を誇張して図示したり一部の部材を省略したりして図示している箇所もある。 【0017】 〔第1実施形態〕 図1は、第1実施形態に係る携帯情報端末テーブル10を示す図である。 図1に示すように、第1実施形態に係る携帯情報端末テーブル10は、携帯情報端末P(例えば、スマートフォン、図3参照)を上に載せることができる折畳み可能なテーブル20と、使用者U(図3参照)の肩にかけてテーブル20を使用者Uの身体前面に支持できるストラップ30と、を備える携帯情報端末テーブル10である。 【0018】 図1に示すように、テーブル20は、端部において相互に回動可能に軸着された複数の棒状フレーム21、22、23、24と、棒状フレーム21、22、23、24が展開した場合に棒状フレーム21、22、23、24間で展張される布材又はビニール布材による幕部25と、を有し、複数の棒状フレーム21、22、23、24の展開時には方形状のテーブル20を形成すると共に、複数の棒状フレーム21、22、23、24の折り畳み時には棒状体を形成する(図2(C)参照)。 【0019】 図1に示すように、ストラップ30は、テーブル20の対角線の両端の部位(図1中、テーブル20の左下と右上)に取り付けられ、展開時には、ストラップ30を使用者Uの肩にかけて棒状フレーム21、22、23、24を展開させてテーブル20を形成し、テーブル20の上に携帯情報端末Pを載せて携帯情報端末Pを操作可能とする。 【0020】 従って、第1実施形態に係る携帯情報端末テーブル10にあっては、折り畳み時は棒状体となるためコンパクトに持ち運ぶことができ、使用時には使用者Uの身体前面に方形状の大きなテーブル20を展開することができる。 【0021】 携帯情報端末テーブル10は、対向する一対の棒状フレームを二組備えている。1つ目の組S1には、棒状フレーム21、22が含まれており、2つ目の組S2には、棒状フレーム23、24が含まれている。二組の棒状フレーム(棒状フレーム21、22と棒状フレーム23、24)は、端部同士が軸部26により回動可能に接続されている。 【0022】 対向する一の一対の棒状フレーム21、23には、それぞれ溝部27が長さ方向に沿って開設され、対向する他の一対の棒状フレーム22、24の端部に設けられ、互いに対角線上において配置された一の一対の軸部28は、溝部27内にスライド可能に配設されて移動軸部として構成されると共に、対向する他の一対の棒状フレーム22、24の端部に設けられた他の一対の軸部26は固定軸部として構成され、棒状フレーム21、23の溝部27内には、一の一対の軸部28を常時、端部外方へ付勢するスプリング29が配設されている。 【0023】 従って、第1実施形態に係る携帯情報端末テーブル10にあっては、収納時には、軸部28を中心に回動させて棒状フレーム21、22、23、24を重ねて一本の棒状体にし、この状態で収納して持ち歩くことができる。また、収納時は、軸部28がスプリング29を圧縮した状態で溝部27内の端部に位置することとなる。 【0024】 幕部25は、透明、不透明、色付き、又は、ハーフミラーのいずれかである。 従って、第1実施形態に係る携帯情報端末テーブル10にあっては、幕部25のバリエーションを増加させることができる。 【0025】 棒状フレーム21の両端部及び棒状フレーム22の下側の端部には、ストラップ用の孔31が形成されている。通常は、テーブル20の右上から左下にストラップ30を掛けて使用するが(ストラップ30の実線参照)、テーブル20の右上から左上にストラップ30を掛けても使用できるようにしている(ストラップ30の破線参照)。また、棒状フレーム21には、指を添えるための突起部32が形成されている。第1実施形態の携帯情報端末テーブル10は、フレームスライド式である。 【0026】 図2は、第1実施形態に係る携帯情報端末テーブル10の展開時、格納中及び格納時の状態を示す図である。なお、図2においては、ストラップ30及びストラップ用の孔31については、図示を省略している。 図2(A)に示すように、展開時には、軸部28は溝部27の外方に位置し、複数の棒状フレーム21、22等は、方形状のテーブル20を形成する。 図2(B)に示すように、格納中には、軸部28は溝部27の内部を内方に移動し(スライドし)、軸部28によってスプリング29は圧縮される。 図2(C)に示すように、格納時には、軸部28は溝部27の内方に位置し、複数の棒状フレーム21、22、23、24は、重ね合わされて棒状体となる。 【0027】 図3は、第1実施形態に係る携帯情報端末テーブル10の使用方法を示す図である。携帯情報端末テーブル10は、以下に示すような様々な場面で使用することができる。 図3(A)に示すように、携帯情報端末テーブル10は、交通機関利用時に使用することができる。使用者Uは、起立した状態でストラップ30を肩にかけ、身体前面にテーブル20を展開し、テーブル20の上に携帯情報端末Pを載せて携帯情報端末Pを操作することができる。図3(A)の使用例では、ストラップ30は、使用者Uの首の後ろから一方側は肩の上を介して、他方側は脇の下を介して、胸前にくるように配置することができる(以下の図3(C)の使用例でも同様)。 【0028】 また、図3(B)に示すように、携帯情報端末テーブル10は、座席に着座する際に使用することができる。使用者は、着座した状態でストラップ30を肩にかけ、身体前面にテーブル20を展開し、テーブル20の上に携帯情報端末Pを載せて携帯情報端末Pを操作することができる。図3(B)の使用例では、ストラップ30は、使用者Uの首の後ろから両肩を介して胸前にくるように配置することができる。 【0029】 さらに、図3(C)に示すように、携帯情報端末テーブル10は、一方の手で荷物を持っている場合に使用することができる。使用者は、左手に荷物を持った状態でストラップ30を肩にかけ、身体前面にテーブル20を展開し、テーブル20の上に携帯情報端末Pを載せて携帯情報端末Pを操作することができる。 【0030】 以上説明したように、第1実施形態の携帯情報端末テーブル10にあっては、折り畳み時は棒状体となるためコンパクトに持ち運ぶことができ、使用時には使用者Uの身体前面に方形状の大きなテーブル20を展開することができるため、携帯情報端末P(例えば、スマートフォン)を屋外で操作する場合、特に、電車やバス等の交通機関利用時に携帯情報端末Pを操作する場合、片手で携帯情報端末Pを支持する必要がなく、携帯情報端末Pの操作が行いやすい(図3(A)参照)。また、座席に着座する際等に一方の手で携帯情報端末Pを支持し、他方の手で携帯情報端末Pの操作を行う場合には、両方の手が体の両側に張り出し、両側に座っている人の迷惑になる可能性があるが、第1実施形態の構成によれば、携帯情報端末Pを自分の身体の前に配置できるテーブル20の上に載せた状態で、片手で携帯情報端末Pの操作ができるため、片手で携帯情報端末Pの支持を行う必要がないことから非常に便利であり、かつ、他人に迷惑をかける可能性も低減できる(図3(B)参照)。さらに、一方の手で荷物を持っている場合にも、荷物を持ったままで携帯情報端末Pの操作、文字入力を行うことができる(図3(C)参照)。 【0031】 また、第1実施形態の携帯情報端末テーブル10にあっては、収納時には、軸部28を中心に回動させて棒状フレーム21、22、23、24を重ねて一本の棒状体にし、この状態で収納して持ち歩くことができ、また、収納時は、軸部28がスプリング29を圧縮した状態で溝部27内の端部に位置することとなるため、使用時には、手で棒状フレーム21、22、23、24を開くと、圧縮したスプリング29が開放され、付勢力により軸部28を押圧し、軸部28は溝部27内を他端部方向へ移動することにより、他の一対の棒状フレーム22、24は一の棒状フレーム21、23と共に方形枠を形成し、その間に展張された幕部25も展開し、携帯情報端末Pが置けるテーブル20を形成することができる。 【0032】 さらに、第1実施形態の携帯情報端末テーブル10にあっては、幕部25は、透明、不透明、色付き、又は、ハーフミラーのいずれかであることから、幕部25のバリエーションを増加させることができるため、様々な用途に適した幕部25とすることができる。 【0033】 〔第2実施形態〕 次に、第2実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、第1実施形態と同様の部分には、同一の符号を付して、重複する説明を省略する。 図4は、第2実施形態に係る携帯情報端末テーブル10−2を示す図である。 第1実施形態と第2実施形態との異なる点は、第2実施形態の携帯情報端末テーブル10−2が、棒状接続フレーム40を備えている点である。その他の点は、第1実施形態と同様である。第2実施形態の携帯情報端末テーブル10−2において、対向する他の一対の軸部26、26の間には、棒状接続フレーム40が、軸部26に対して回動可能に配置されている。 【0034】 このように、第2実施形態によれば、棒状接続フレーム40が斜めに配置されるため、斜めに配置された、棒状接続フレーム40により、展開時における全体の強度が増大する。 【0035】 〔第3実施形態〕 次に、第3実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、第1実施形態と同様の部分には、同一の符号を付して、重複する説明を省略する。 図5は、第3実施形態に係る携帯情報端末テーブル10−3を示す図である。 第1実施形態の携帯情報端末テーブル10は、フレームスライド式であったが、第3実施形態の携帯情報端末テーブル10−3は、扇子式である。第3実施形態の携帯情報端末テーブル10−3において、複数の棒状フレーム51、52、53、54、55、56、57は、それぞれ異なる長さの部材により形成され、端部において単一の軸部58により回動可能に軸着されている。 【0036】 図5(A)に示すように、複数の棒状フレーム51、52、53、54、55、56、57は、収納時には単一の棒状体を形成すると共に、図5(B)に示すように、展開時には、棒状フレーム51、57が方形状のテーブルの一片部及び隣接する他片部を形成し、他の棒状フレーム52、53、54、55、56はその間に配置される。 【0037】 このように、第3実施形態に係る携帯情報端末テーブル10−3によれば、使用時には正確に方形状に展開可能であるため、テーブル20については扇子の方式を利用して展開させながら、使用時には扇状ではなく携帯情報端末Pを置きやすい方形状に展開可能である。 【0038】 上述した各実施形態は、以下の変形が可能である。 (1)携帯情報端末Pは、スマートフォンの例で説明したが、タブレット等であってもよい。 (2)テーブル20は、長方形状に展開可能であってもよく、正方形状に展開可能であってもよい。 (3)棒状フレームの形状や長さは、任意に変更可能である。また、各棒状フレームの接続の順番も、任意に変更可能である。 【産業上の利用可能性】 【0039】 本考案は携帯情報端末テーブルに係ることから、広く産業上の利用可能性を有している。 【符号の説明】 【0040】 10、10−2、10−3 携帯情報端末テーブル 20 テーブル 21、22、23、24、51、52、53、54、55、56、57 棒状フレーム 25 幕部 26、28、58 軸部 27 溝部 29 スプリング 30 ストラップ 31 ストラップ用の孔 32 突起部 40 棒状接続フレーム P スマートフォン S1 1つ目の組 S2 2つ目の組 U 使用者 |
【図1】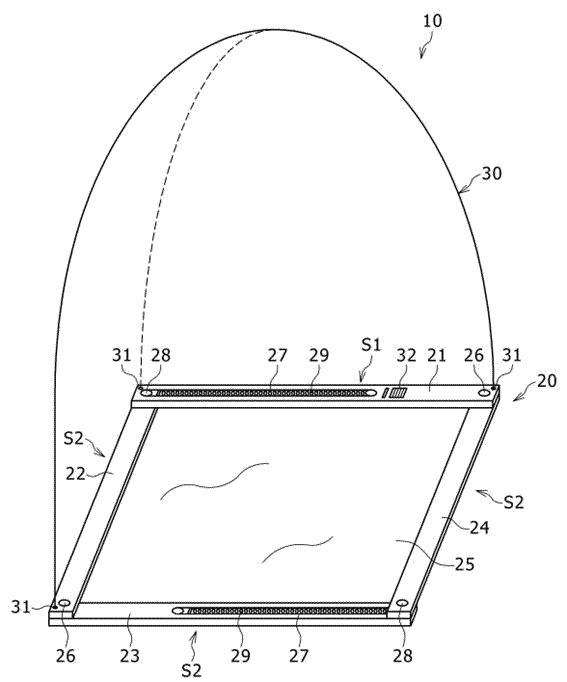 |
【図2】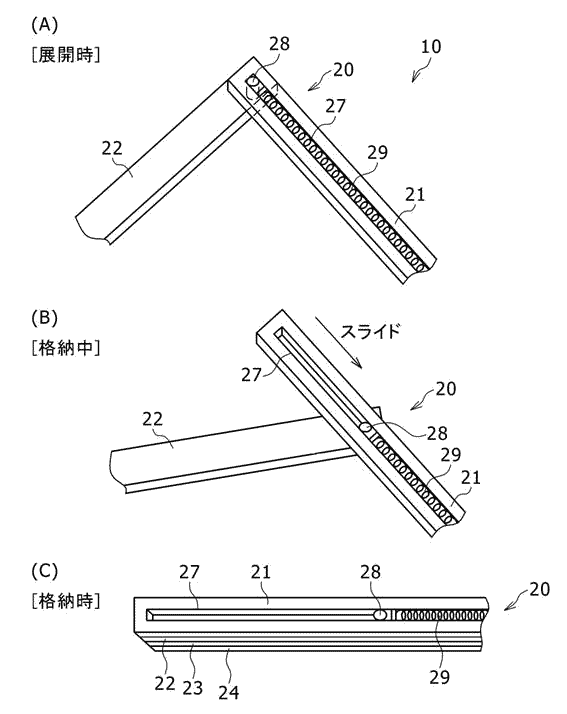 |
【図3】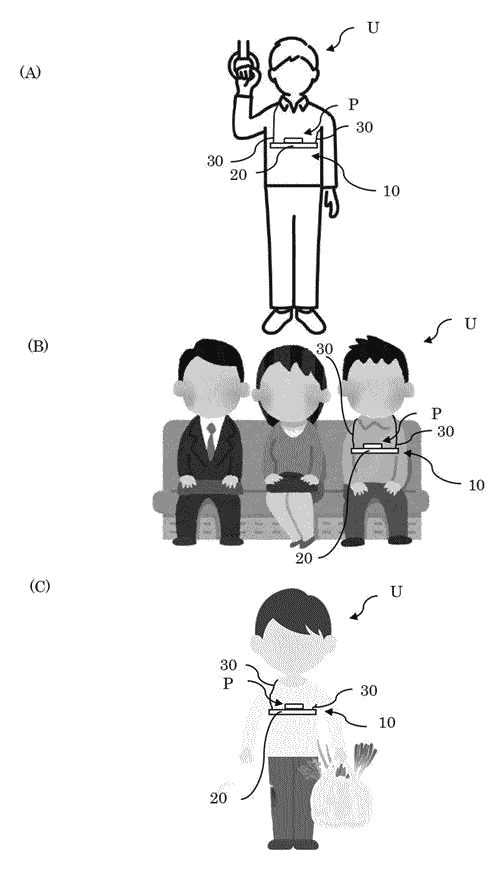 |
【図4】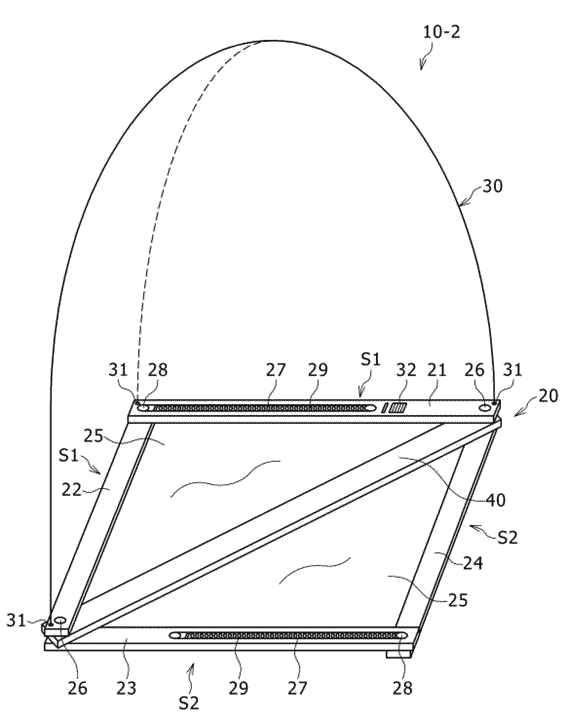 |
【図5】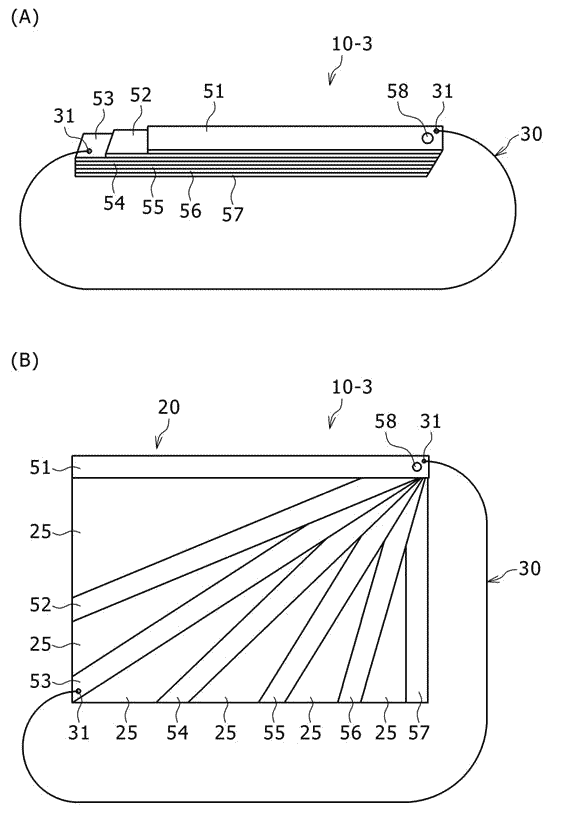 |
| ページtop へ |